こんにちは
あんきもです
最近は動画の方ばかり作っていて、こちらもそろそろ書かないと…
と焦っている今日この頃です
夏といえば
金魚!メダカ!
このお魚はよく飼われだす印象があります
なので、初夏の内からこの記事を掲載して考えの足しになれればと思いました
是非とも最後まで読んでいって下さい
オトシンクルスは混泳向き?
そもそもオトシンクルスについてあまり知らない方へ
簡単にまとめてみました
オトシンクルスは比較的温和なお魚です
他のお魚を襲うことはまずありません

金魚やメダカの卵を食べるといった話も聞きませんね
メダカに関しては稚魚水槽に入れても、稚魚を食べることはありませんでした。
(お魚は口に入れば食べてしまうことが多いので、参考までに)
水質は、中性~酸性を好むため多くの淡水魚の飼育環境に合わせることが可能です
表層~中層を泳ぐお魚に対して、オトシンクルスは底層や壁面についていることが多いので、住み分け可能です
最たる特徴として、壁面に付く茶ゴケをよく食べます。
これを目当てで飼育する方も多いでしょう
ただ、水質の変化にはかなり弱い面があるので、点滴法などの慎重な水合わせが必要です。
これを気にする方がいますが、そもそも新しく迎えたお魚は慎重に扱うべきなので、丁寧にできていれば恐れることはありません
(あと、ショップの水質とどれだけ違うかも導入の成否に関係しますので、どんなお魚でも慎重に!)
あとは、こちらの記事にまとめてあります
熱帯魚と日本淡水魚の混泳は可能?
可能です!
もちろん
水温が低い場所に生息するお魚は難しいかもしれません。
混泳に向いた温和な種類であれば熱帯魚との飼育は可能です。
例えば、ネオンテトラやグッピーなどの様々なお魚の中に混ざって泳いでいる熱帯魚は、混泳向きの熱帯魚と言えるでしょう。
それでも組み合わせの良し悪しはありますね。
それは日本の淡水魚にも言えます。
ハゼの仲間は大きさの近いお魚に攻撃的だったりするので複数飼育は難しいです。
サイズに大きな違いがあれば、温和なお魚であっても食べてしまうことがあります。
考え方は日本淡水魚と熱帯魚で大きく違うことはありません。
食べている飼料も同じものを使えることが多いので、難しく考えなくて良いと思います。
ただ、ヒーターは必須です。
個人的な意見ですが
日本淡水魚にも金魚やメダカであれば、ヒーターはあった方が良いと思っています。
(屋外飼育などもあるので、あくまで個人の意見です。強要したいわけではありません)
金魚とオトシンクルスは混泳可能?
金魚とオトシンクルスの混泳はやめた方がいいです。
これは、他で上手くいっている方がいたとしても、やめた方がいいと思っています。


その理由は、いくつかあります。
3つに簡単にまとめてみました
理由 その1 粘膜舐め
オトシンクルスが金魚の粘膜を舐めるから
オトシンクルスは他のお魚を襲うことはありません。
しかし、体表の広い魚の体を舐めることがあります。
お魚の体表を覆う粘膜は、ヒトのもつ粘膜と同じくバリア(生体防御)として働いています。
これを削られてしまうと体調不良や大きなストレスになります。
つまり、オトシンクルスが金魚に対して、結果として害をなすことがあるのでやめるべきです。
理由 その2 誤飲
金魚がオトシンクルスを飲み込むから
金魚の混泳はそもそも難しいと私は考えます。
それは、金魚がなんでも口に入ったものを飲み込むお魚だからです。
基本的に、お魚は口に入れば食べてしまうことが多いです。
そして、金魚はその特性が強いです。
金魚を長く飼育されている方は、底床にはかなり気をつけていると思います
小石を金魚が誤って飲み込み、取り出せなくなった経験がある方もいるでしょう
これは別に金魚が悪いわけではなく、飼育者が気をつけるべき点です。
そして、オトシンクルスを金魚が飲み込んだ場合ですが…
最悪どちらも亡くなります。
オトシンクルスの骨格は、頭部やヒレで引っかかると後ろに引き抜くことができません。
金魚がオトシンクルスをに飲み込むときは必ず頭から飲みます。
そのため、ヒレなどが返しになって抜けなくなります。
意外と金魚は口を大きく開くことができますで、なんとなく平気だと思っていても飲み込まれる場合があります
つまり、金魚がオトシンクルスに対して、結果として害をなすことがあるのでやめるべきです。
理由 その3 衰弱
これは、オトシンクルスの特徴に由来するのですが
オトシンクルスが弱ってしまう
金魚はかなりよく食べます。
オトシンクルスの餌付けの成否に関わらず、オトシンクルスにまわってくる餌がなくなることでしょう。
あと、金魚は水を汚しやすいので、水質の変化によってオトシンクルスが体調を崩します。
対策は可能でしょうが、上記の理由を踏まえると混泳は避けたいです。
メダカとオトシンクルスは混泳可能?
オトシンクルスは混泳可能です
ただ気をつけるべきことが多いのも事実です。
その前に、どのお魚を混泳するときも必ず考えておくべきことがあります。
それが優先順位
とくに生活圏が異なるお魚の場合は考えるべきです。
難しく考えず、どのお魚に飼育の焦点を当てていくか、これを考えましょう
これがぶれてしまう方が飼育に失敗しやすいです
それでは、
混泳上での注意点をあげていきます。
ちなみに、ヒーターは必須です


注意点 その1 痩せ
オトシンクルスが痩せやすい
オトシンクルス用にごはんを与えても、かなり高い割合でメダカにとられます
対策として深夜に与える方法をとると少しはマシです
他にはオトシンクルスを1匹から始め、餓死をしない環境を作ってあげると良いかと
野菜等を与えるなどの方法がありますが、私はあまり勧めません
上記した優先順位が、
オトシンクルス優位であるならば、多少メダカが肥えても多めに餌を与えることが方法としてはあります。
現に私はそのような飼育方法でした。
注意点 その2 餌の違い
与える人工飼料の種類が異なる
オトシンクルスはコケを食べると良く知られていますが、人工飼料にも十分餌付きます
正直なんでも食べると思いますが、慣れない内はコリドラスの餌やプレコの餌を勧めます
他には、底生魚用の餌もいいですね
これらの餌は、沈下性の餌です
一方で、メダカの餌は表層に浮いているタイプが多いでしょう


同じものを使えないか、と思われるでしょうが
最初は確実性の高いものを使用するのが良いですね
ちなみに、コリドラスの餌は栄養価が高いものが多いので肥えやすいです
繁殖期のメダカのメスには良いかもしれませんが、結構肥えますので…
それは知っておいて下さい
注意点 その3 生活圏
生活圏の違いによる飼育環境
オトシンクルスは水質の変化や悪化に弱いです。
そのため、安定して長期飼育するためには水をどのように維持していくかが大切です
ろ過は多い方が良いのですが、メダカは水流が速いとストレスになるので弱ります。
ろ過を増やすとそれによる水流が発生します。
オトシンクルスは底生魚なので、エアレーションで下から上に向けての水流がある循環は必要です。
そのため、どちらも叶える広い水槽が望ましいです。
他には、水草等の水流をある程度さえぎる遮蔽物はあるといいかもしれませんね。


注意点 その4 いじめ
メダカは個体によってはつつきます
私はメダカを10年以上飼育しています。
よく見る問題行動の1つとして、他のお魚をつつきます
とくに成熟したオスや大きい個体はその傾向にあります
これはメダカに限ったことでなく、遊泳するお魚で見られる傾向なので、それも1つの特徴として考えましょう。
隠れ家が少ないと追い払われることやつつかれることがあります。
オトシンクルスには結構ストレスらしく、それが原因で拒食になることがあります。
お気をつけ下さい。
まとめ
いかがでしたか?
そもそも熱帯魚と日本淡水魚の混泳が可能か疑問を持つ方がいると思うのですが…
淡水魚と括って見ると混泳の仕方は同じだと私は考えています。
混泳が難しいお魚は日本淡水魚と熱帯魚関係ないお話です
正直、混泳という行為自体が飼育難易度を上げるので、何かしらの問題が生じます。
それがないことが珍しいので、分からない内は恐る恐る行うくらいが丁度いいくらいです。
問題ないと言われていても、観察してみると上手くいっていなかったりもします。
これが個性や時期によるものだったりするので、しっかりと観察するのは大切です。
オトシンクルスがご飯を食べなかったり、困ったことになりましたら、他の記事も見てくださいね(*´ω`*)
一方で、金魚やメダカについての記事をしっかり読みたい方は、他のサイトの方が充実していることでしょう!
……
……気が乗ればそのうち書きます……
もっと頑張らないとですね
今回はここまで
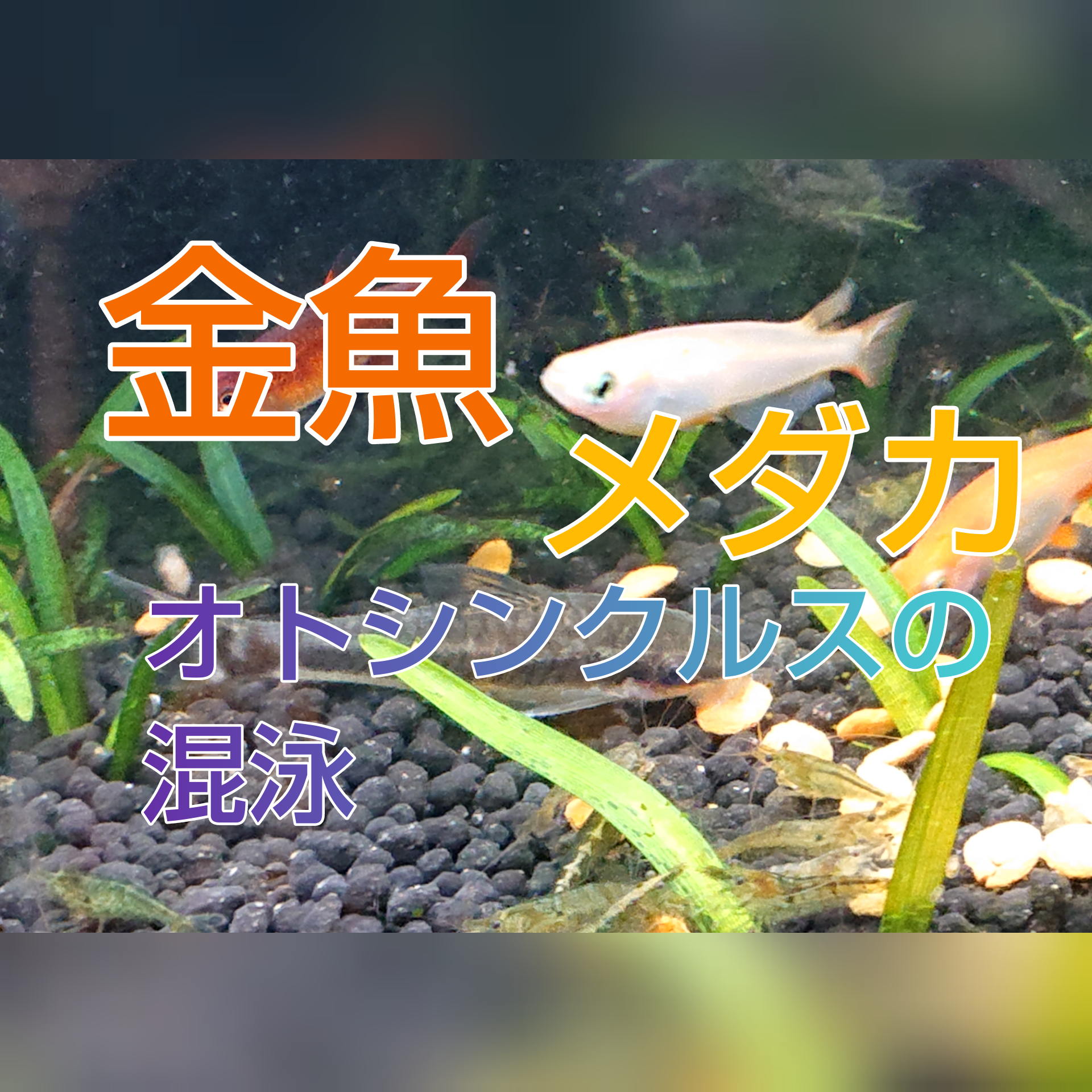



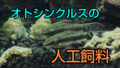
コメント